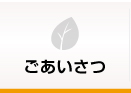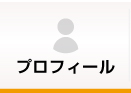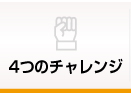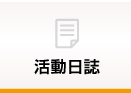第5期
2025年
2024年
第4期
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
第3期
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
第2期
2014年
2013年
2012年
2011年
第1期
2010年
2009年
2008年
2007年
平成27年9月定例会 一般質問
質問事項
2015年10月9日
●グローバルリーダーズハイスクール
公明党大阪府議会議員団の加治木一彦でございます。
今回、一般質問の機会をいただきましたので、順次質問をさせていただきます。
まず、グローバルリーダーズハイスクールについてお伺いします。
府は、豊かな感性と幅広い教養を身につけ、社会に貢献する志を持つ知識を基盤とするこれからのグローバル社会をリードする人材を育成するとの理念のもと、平成23年、10校に文理学科を設置しました。育成されるべき力として、①幅広い教養と高い専門性②高い志--社会貢献--と豊かな人間性③英語運用能力、の3つを掲げ、各学校独自の取り組みと10校共通の取り組みがなされています。
これまで、10校とも文理学科、普通科を併設しておりましたが、平成28年度の入学生からは、北野高校と天王寺高校の2校については全員を文理学科の生徒として募集することになったと聞いております。なぜ、この2校を全て文理学科として募集するのでしょうか、教育長に伺います。
グローバルリーダーズハイスクール、いわゆるGLHSにおけます文理学科の拡充につきましてお答えをいたします。
大阪府教育委員会といたしましては、グローバルリーダーズハイスクールがさらに充実をし、グローバル人材育成を進めるとの考えから、大阪府教育振興基本計画におきまして、平成25年度以降の目標といたしまして、グローバルリーダーズハイスクールとしての最初の卒業生が出る時期を見据えた上で、文理学科の拡充を検討することといたしております。
平成26年3月に初めての卒業生を送り出したことを受けまして、外部有識者によります評価審議会におきまして、大学進学実績や外部コンテスト等の実績をもとに、同年7月、当該10校の3年間の総合評価を行いました。この評価を踏まえまして、大阪府教育委員会におきまして、文理学科の拡充について検討を重ねてきたところでございます。
北野高校と天王寺高校につきましては、当該10校が共通に実施をいたしますテストの結果、また進路実績から、第一に、難易度の高いカリキュラムに十分対応できる生徒が全学的に在籍をしていること、第二に、評価審議会の評価が他の8校と比較をして格段に高いこと、第三に、普通科においても文理学科に匹敵をする質の高い教育活動を行っていること、以上のことから、平成27年2月20日の教育委員会会議におきまして、両校について全ての学級を文理学科として募集することを決定したところでございます。
グローバルリーダーズハイスクールは、進学実績だけでなく、高い志や豊かな感性を育むといった理念を達成するべく、多面的な教育活動に取り組まれています。例えば、課題研究は、2年生の1年間、小グループや個人でテーマを決めて研究し、発表するだけでなく、生徒同士で質問し合い、意見交換をするというものです。大学の進学実績を上げることだけを目的にするなら、回り道にも思えますが、生徒一人一人の長い人生を見渡せば、みずからテーマを決めて解決策を考えるという取り組みは、大きな自信につながると考えます。
グローバルリーダーズハイスクールには、外部有識者で構成する評価審議会が総合評価を出しています。ことし(平成27年)は、6月12日に審議会が開催され、26年度の各学校の取り組みや実績について評価がなされました。AAA、AA、A、B、Cの五段階による総合評価でBやCがつけられた学校はありませんが、学校ごとの評価シートを詳しく見ると、教員に関する評価で気になる表現がありました。
具体的には、教員の学校経営への参画意識の形成が今後充実していく上での課題、教員の学校運営に対する参画意識を高めることに課題といったものです。このような教員の参画意識に対する指摘に対し、府教育委員会としてどう認識し、改善していくのでしょうか、教育長に伺います。
GLHSにおける学校経営への教員の参画意識についてお答えをいたします。
評価審議会では、これら10校におけます教員の指導力につきまして、教科を超えた学校全体での授業研究、教材作成の取り組みなど良好な評価をいただいております。その一方で、教員の学校経営への参画意識の向上が課題であると評価をされた学校も一部にございます。
教員の参画意識は、全ての学校におきまして重要でございますが、とりわけグローバルリーダーズハイスクールは、教育の先進的な取り組みを目指します学校でありますことから、より一層全教員が一体となった組織的な取り組みが必要であると認識をいたしております。課題が指摘をされた学校におきましては、評価審議会の指導と助言を踏まえまして、現在、学校の問題点を共有し、その改善に向けて全ての教員がグループディスカッションを行うなどの取り組みを進めてきております。
当該校が、校長のリーダーシップのもとでPDCAサイクルを有効に機能させ、教員の参画意識を高めながら組織的に教育活動に取り組んでいけますように教育委員会として支援に努めてまいります。
2015年10月9日
●スーパーイングリッシュティーチャー
次に、この4月から府立高校に配置されたスーパーイングリッシュティーチャー--SETについて伺います。
府は、今年度から骨太の英語力養成事業として、高校3年間での英語学習の到達レベルを生徒が英語圏の大学に進学できる程度にまで読む、聞く、書く、話すの4技能を引き上げることを目標に、TOEFL iBTなどを活用した英語教育を始めました。教員免許の有無にかかわらず、高い英語力を持った人材をSETに採用し、今(平成27)年度は10校、来(平成28)年度は7校の計17校に配置します。
私は、平成26年2月定例会の一般質問で、高校における英語力の養成を取り上げた際、SETの応募、採用状況を問いただし、ぜひとも優秀な人物に来てほしい、人数確保を優先する余り、SETもどきを採用しないようにと強く求めました。
そこで、実際にSETがどのような授業をされているのか、知事と教育長は、千里高校に行かれたそうですが、私は、6月25日に箕面高校、7月14日に北野高校に伺いました(スライド1、2)。箕面高校の一年生の授業は、30代の男性SETが、生徒に自分の好きな歌手やグループについて15秒間考えて45秒間英語で話すことや、J-POPとK-POPのどちらが好きかを英語で説明する練習などをしていました。女子生徒が多数を占めるクラスで、興味を持ちやすいテーマとして若者向けの音楽を選び、英語を話す練習をするという点に工夫を感じました。
北野高校は、ネイティブの女性のSETと日本人の英語科教員が、2人一組で授業を進めていました。最初に、英語の本を十分ほど黙読し、感想などを生徒同士が英語でやりとりしていました。また、この日は、夏休みの予定を英語で話す時間があり、生徒同士がやりとりをする前に、日本人教員がSETの質問攻めに遭うという場面がありました。日本人教員が、みずから生徒にお手本を示そうとしている点に強く関心を持ちました。
ほかのSETの皆さんも、それぞれに工夫を凝らした授業をされているとお聞きしております。それらは、もとからいる英語科教員には思いつかなかったことかもしれませんし、したくてもさまざまな制約があってできなかったことかもしれません。配置されてまだ半年ほどのSETですが、それぞれの学校で変化が生まれているとお聞きしております。
SETを配置した効果は、どのようなことがあるのでしょうか、また配置校以外の英語科教員に対してSETのノウハウやスキルをどのように広めようとしているのでしょうか、教育長に伺います。
スライド1
スライド2
スーパーイングリッシュティーチャー、いわゆるSETについてお答えをいたします。
SETにつきましては、今(平成27)年度から府立高校10校に配置いたしまして、聞く、話す、読む、書くの4技能をバランスよく高めるため、TOEFL iBTを扱った実践的な授業を行ってきております。配置校におきましては、ふだんから英語科教員がSETの授業を見学し、SETが講師を務めます校内研修に参加することで刺激を受け、4技能を高める指導法の研究、実践や教材開発に積極的に取り組んでいるところでございます。
また、他校の英語科教員を対象としたSETによる公開授業を実施した上で、その後、意見交換を行っており、参加者は、生徒の英語力やコミュニケーション能力を高める指導法を習得し、自校におけます授業実践に生かしてきております。
今後は、SETの授業を動画録画したものを大阪府教育センターのホームページに掲載いたしまして、全ての府立高校において閲覧できますように検討しております。
今年度、議員には、SET配置校2校を御視察いただきまして、評価をいただいたことを心強く思っております。ありがとうございます。28年度は、さらに7校にSETを配置することといたしておりまして、今後ともSETによる研修や公開授業を計画的に進めますとともに、生徒の英語力向上に向けましたシラバスや教材の開発を行うなど、さらなる成果の普及に努めてまいります。
2校のSETの授業は、大変に興味深く、内容の濃いもので、あっという間に時間が過ぎていきました。私も、高校生に戻って一緒に受けたい、私の高校生時代にこんな授業があったらどんなによかったかと感じた次第です。
SETの配置校には、高校3年間で英語圏の大学に進学できる実力を生徒が身につけるという非常に高い目標が設定されています。生徒が、それだけの英語力をつけるには、授業以外でも英語を必死に学ぶ必要があるでしょう。SETによる授業の効果を生徒が最大限に受けられるよう、各校でのさらなる工夫をお願いしておきます。
2015年10月9日
●百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録
次に、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録について伺います。
我が会派の代表質問でも取り上げましたが、4世紀末から5世紀にかけて築造された百舌鳥・古市古墳群は、古墳時代を代表し、1500年の時を超え、大阪が世界に誇れる歴史遺産だと考えます。
私も、先月、地元淀川区の方々と初めて仁徳天皇陵古墳の拝所を訪れるとともに、堺市博物館で古墳からの出土品などを見学しました。以前、警察常任委員会の管内視察でヘリコプターに搭乗し、空から仁徳天皇陵を眺めましたが、今回は、堺市役所の展望台と拝所で仁徳天皇陵の存在感に圧倒されました。来年の国内推薦の獲得に向け、推薦書原案をよりよいものに改訂するとともに、登録に向けた機運がより一層高まるように取り組んでいただきたいと考えます。
まずは、多くの人が百舌鳥・古市古墳群に実際に足を運び、そのスケールの大きさを実感し、大阪の歴史に思いをはせてもらう、古墳群の魅力を体感してもらう取り組みが重要ではないでしょうか。
また、小学校高学年で日本の歴史を学ぶことから、仁徳天皇陵古墳などを校外学習や遠足で訪れてもらい、子どもたちに歴史や魅力を現地で直接触れる機会をつくることが非常に有意義と考えます。あわせて、府民文化部長のお考えを伺います。
百舌鳥・古市古墳群を将来へと引き継いでいくためには、地元のみならず、広く多くの方々にその価値や魅力を知っていただく必要があるということから、議員御指摘のとおり、実際に古墳を訪れていただき、その雄大さをじかに感じていただく取り組みが大変重大だというふうに考えております。そのため、府政だよりやホームページによる情報発信はもとより、府と地元3市で構成する推進本部会議におきまして、古墳群を周遊できるウオーキングマップを作成し、市役所や最寄り駅等に配架しております。ぜひ、御活用いただきたいと思います。
また、大坂の陣400年天下一祭の一環として実施する大阪の歴史を体感できるウオーキングイベントのコースに取り入れるなど、今まで余りなじみのなかった方々にも、古墳群を訪問していただけるよう取り組んでおります。
さらに、次代を担う子どもたちに百舌鳥・古市古墳群の魅力を実感してもらうため、遠足等の候補地にしていただけるよう、その魅力やモデルコースなどを府教育委員会に御協力いただき、市町村教育委員会にお知らせしていきたいと存じます。
済みません、教育長も御協力お願いいたします。
私が、堺市博物館を訪れた日は、「イタスケ古墳を守ろう-破壊から保存、そして世界文化遺産へ-」と題した企画展をされていました。第2次大戦後の混乱期、戦後復興の名のもと、開発行為で多くの古墳や遺跡が破壊されました。イタスケ古墳も、住宅地開発のため、破壊されそうになったときに、考古学者や市民らが立ち上がり、紆余曲折を経て国史跡として保存され、今に至ります。ことし(平成27年)は、日本の文化財保存運動の先駆けとして高く評価されているこの保存運動から60年の節目に当たります。
改めて、先人が残した歴史の重みをかみしめるとともに、後世に百舌鳥・古市古墳群を引き継いでいけるよう、世界文化遺産の認定に向け、府がしっかり力を入れて取り組んでいくことをお願いしておきます。
2015年10月9日
●日本遺産認定の推進
次に、日本遺産認定の推進について伺います。
文化庁は、昨年度、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化、伝統を語るストーリーを日本遺産として18件認定しました。日本遺産には、1市町村が単独で認定を受ける地域型と複数の市町村にまたがるシリアル型の2種類があります。
例えば、京都府はシリアル型で、宇治市や城陽市など8市町村にまたがり、茶畑やお茶の問屋街、茶祭りなどを一つにまとめた「日本茶800年の歴史散歩」、兵庫県篠山市は地域型で、デカンショ節や篠山城跡、焼き物窯などをもとに「丹波篠山デカンショ節-民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶」というストーリーが日本遺産に認定されました。従来の文化財行政が、個々の美術品や建築物、伝統芸能を点で指定し、保存を重視していたため、地域の魅力が十分に伝わらなかったとの反省を踏まえたもので、遺産を面で捉え、地域のブランド化、アイデンティティーの再確認につなげようというものです。
文化庁は、今後もふえ続けることが見込まれる訪日外国人旅行者に日本各地を周遊してもらい、地域の活性化に結びつけるため、受け皿となる日本遺産を日本各地で認定する一方で、ブランド力維持のため、件数の制限を考えており、平成32年までに合わせて100件程度の日本遺産を認定する予定です。日本遺産として認定を受ければ、魅力発信推進事業として、①情報発信、人材育成②普及啓発③調査研究④公開活用のための整備、といった事業に国から文化芸術振興費補助金が交付されます。大阪府や府内市町村にとっても、指定を受けることに大きなメリットがあると考えます。
ところが、昨(平成26)年度の第一回公募に、大阪府内の市町村から申請は全くなかったとのことです。近畿2府4県で日本遺産がないのは、大阪府と和歌山県という状況です。
府は、市町村が手を挙げるよう促すことや、また複数の市町村をまとめて府がみずから申請するなど積極的に取り組んでいくべきと考えますが、いかがでしょうか、教育長のお考えを伺います。
日本遺産についてお答えをいたします。
文化財を核とした日本遺産の認定につきましては、地域の魅力創出や観光集客に極めて有効であると考えております。大阪府内には、全国第5位となります785件の国指定の有形無形の文化財がありまして、日本遺産の認定に向けたポテンシャルは高いとも考えております。
日本遺産の申請につきましては、原則市町村が行うこととされておりまして、単独で申請を行う場合には、文化財の保全活用を盛り込みました歴史文化基本構想の策定などの要件が定められております。
大阪府教育委員会といたしましては、この歴史文化基本構想の策定に取り組んでおられます市町村に対しまして、この策定のための委員会に参画する中で、専門的見地から指導助言を行うとともに、いまだ策定していない市町村に対しましては、積極的な取り組みを促しているところでございます。
また、文化財を核として複数の市町村が連携をして行うものにつきましては、大阪府が申請者となることもできますので、本府といたしましても、地域の歴史魅力や特色を示すストーリーを作成できる具体的な候補の掘り起こしを行うなど、積極的に取り組んでまいります。
教育長には、前向きな御答弁をいただき、ありがとうございます。現在、日本遺産認定に向けた取り組みは、教育委員会の文化財保護課が担当しています。地域に根差した文化財を核に魅力あるストーリーを構成できるかが日本遺産認定の鍵を握ることを考えると、大阪の魅力向上や観光集客、まちづくりや産業振興などの要素も深くかかわってくるのではないでしょうか。そのためには、府庁の関係部局が連携して日本遺産認定に取り組むべきと考えます。知事の御所見を伺います。
加治木議員の御質問にお答えをいたします。
大阪には、全国に誇るべき文化財が数多く存在をいたしています。府内の各地域が持つ資源を生かし、日本遺産として発信していくことは、地域のブランド化や都市魅力の向上など地域活性化につながり、ひいては大阪府全体の集客力向上へ期待ができると考えております。
今後は、全庁挙げまして、府内市町村にある魅力的な資源が、日本遺産として認定されるように取り組んでまいります。
2015年10月9日
●アーツカウンシルによる取り組み
ぜひとも、よろしくお願いいたします。
次に、アーツカウンシルによる取り組みについて伺います。
平成25年3月にまとめられた第3次大阪府文化振興計画に、アーツカウンシルを府市共同で設置することが盛り込まれました。統括責任者を公募で選定した後、同年7月から大阪アーツカウンシルが活動を始めました。
アーツカウンシルとは、芸術文化に関する専門家で構成されるもので、第2次大戦直後の1946年にイギリスで設置されたのを第一号に、現在ではノルウエー、シンガポールなどさまざまな国が、日本では文化庁や東京都が同様な取り組みを行っています。行政と一定の距離を保ちながら、芸術文化の専門家が文化事業の評価、審査等を行い、施策のPDCAサイクルを構築する役割があり、大阪にふさわしい文化行政を展開させる上で重要な役割を果たすものと考えます。
設置から2年が経過し、この間、精力的に活動されているとお聞きしておりますが、アーツカウンシルの導入で、本府の文化行政にどのような変化があったのでしょうか、府民文化部長に伺います。
アーツカウンシルの大先輩、アーツカウンシルイングランドは、今から2年前、「Greatartandcultureforeveryone」と題し、2020年までの間で取り組む戦略的枠組みの改訂版をまとめました。アーツカウンシルを芸術に対する公的投資の管理人と役割づけた上で、日々の生活や教育、地域の再生や観光、海外での名声などの面に文化や芸術が最大限の価値をもたらすように取り組む責務があるとしています。
また、①すぐれた文化や芸術が繁栄すること②可能な限り多くの人が文化や芸術にかかわること、の2点をアーツカウンシルのミッションとして挙げています。その上で、子どもや若者たちに芸術活動を体験する機会を保証し、観客、聴衆または将来の芸術家として積極的にかかわれるようにすることが重要であると強調しています。
できてまだ2年少々の大阪アーツカウンシルですが、担うべき役割は非常に大きなものがあると考えます。大阪の芸術文化発展のため、今後どのように継続、展開させていくのでしょうか、あわせて府民文化部長に伺います。
アーツカウンシルにつきましては、2年前の平成25年7月から活動を開始し、大阪府市の全ての文化事業の視察、関係者ヒアリング等を行い、専門的な見地から事業評価や府市に対する改善提案を行うなど、文化事業のPDCAサイクルを構築する上で大きな役割を果たしております。
例えば、補助事業につきまして、補助金を交付するだけではなくて、補助した事業の活動事例を発表してもらう場を設けて、行政と文化事業者がもっとコミュニケーションを図るべきだという提案がありましたので、早速実施しているところでございます。
また、ワッハ上方につきまして、資料館としての機能を充実することが大事だとの御提案を踏まえ、直営化して資料の点検、調査に力を入れております。
また、徹底した現場主義による現状分析から、将来に向けて大阪が直ちに取り組まなければならない文化振興策の企画提案がありましたので、今年度、府市において大阪文化の魅力発信、専門人材の育成等を狙いとする芸術文化魅力育成プロジェクトとして具体化をいたしました。
大阪を拠点に活動するジャンルの異なる事業者が協力して、伝統をキーワードにつくり上げた上方伝統芸能、演劇、音楽、アートなど全部で20プログラムを11月10日までの週末を中心に、大阪市中央公会堂をメーン会場に実施しているところでございます。
こうした文化事業は、継続的に取り組むことにより、次第にその効果があらわれてくるものと存じますので、これからもアーツカウンシルの力を得ながら粘り強く取り組んでいきたいと考えております。
今後、アーツカウンシルには、事業評価はもとより、豊かな文化資源をさらに発展させる牽引役としての役割を果たしてもらいたいと考えておりまして、府としましても、アーツカウンシルが、その機能を十分発揮できるようサポートするとともに、2020年のオリンピック・パラリンピックに向けた国等の文化プログラムへの動きにもしっかりと対応しながら、文化の力が大阪に根づき、そして都市の活力につながるよう取り組んでまいります。
アーツカウンシルイングランドは、2012年ロンドンオリンピック・パラリンピックに合わせて開かれた文化プログラムが、多種多様なすばらしい芸術家や美術館、博物館の所蔵品を世界に紹介する特別な機会となったと振り返っています。東京オリンピック・パラリンピックまでの5年という限られた時間ですが、世界に誇れるすばらしい文化芸術が大阪に数多くあるということを文化プログラムで発信できるよう、ぜひとも大阪アーツカウンシルに頑張っていただきますようにお願いしておきます。
2015年10月9日
●北陸新幹線の大阪延伸
次に、北陸新幹線の大阪延伸について伺います。
北陸新幹線の敦賀から先、大阪までのルートについては、平成25年3月、関西広域連合が、開業までの期間や費用対効果等を勘案し、米原ルートが最も優位であると結論づけました。広域連合でルートを議論していた時期は、経済のデフレ脱却が最優先課題になっており、工事費が安いということも大きな判断要素になったのではないかと思います。しかし、現在は、状況が大きく変わっているのではないでしょうか。
新聞報道によると、JR西日本が新たなルートの内部検討をしており、真鍋精志社長は、9月16日の記者会見で、タイミングが来れば最適と思うルートを申し上げると発言しています。国も、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームが、敦賀・大阪間整備検討委員会を立ち上げ、2年以内に結論を出すべく、敦賀以西のルートの検討を開始するなど北陸新幹線の早期整備に対し、非常に大きなうねりが起こってきています。
また、将来の大阪のあるべき姿を見通し、国土の発展や首都直下型地震のときに大阪がその代替機能を果たすなど、グランドデザインを描く中に北陸新幹線を位置づけるべきと考えます。
地図をごらんください。(スライド3)
現在、首都である東京からは、放射状に新幹線ネットワークが構築され、東京駅から25府県へ乗りかえなしで行ける一方、新大阪駅からは15都府県、つまり東京から鹿児島、この15都府県にとどまっています。
大阪が、東京と並ぶ我が国の交通ネットワークの中核としてさらに発展していくためにも、北陸新幹線の大阪までの早期開業が急務であると考えます。大阪府として、北陸新幹線への取り組みについて政策企画部長に伺います。
スライド3
北陸新幹線は、日本海側と太平洋側の連携を強化し、国土の発展に寄与する重要な広域交通基盤でございまして、本(平成27)年8月に閣議決定をされました国土形成計画においても、その重要性が位置づけられているところでございます。
また、大阪、関西圏にとりましても、北陸圏との連携交流の強化を図り、地域の成長を一層促進していくために、一日も早く大阪へつなげることが必要であるというふうに考えているところでございます。
本府といたしましても、国等の検討状況を注視しながら、フル規格による大阪までの早期全線開業の実現に向けまして国への働きかけを行うなど、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
2015年10月9日
●新大阪、大阪の一体化
この2年間、さまざまな状況変化も予測されますので、しっかりと情報収集等をお願いいたします。
次に、新大阪、大阪の一体化について伺います。
モニターをごらんください。
昭和36年当時の新大阪駅周辺の空撮写真です(スライド4)。当然、新大阪駅も新御堂筋もできておりません。北側に府立東淀川高校がありますが、昭和30年代前半は、雨が降ったら長靴を履いて登校しなければならない状況で、将来オフィス街に発展するとは想像もつかなかったと当時を知る同校OBの方にお聞きしたことがあります。
現在の新大阪駅は、新幹線や在来線、地下鉄が乗り入れ、一日の乗降客数が40万人、専門学校や、新幹線ですぐ東京に行ける地の利もあり、ベンチャー企業も数多く集まっています(スライド5)。北陸新幹線にとどまらず、リニア新幹線も新大阪駅をターミナルとすることが想定されています。利用者の増加が見込まれる新大阪駅は、大きく変わっていく必要があります。
一方、大阪駅周辺地域は、一日の乗降客数が約250万人の西日本最大の交通の要衝であり、業務、商業の集積地でもあります。この両駅を合わせると、巨大な鉄道拠点となります。
現在、うめきた地区は、平成34年度末の完成を目指した新駅設置事業が始まり、完成すれば関西空港へ行く特急はるかの停車駅となるなど、さらに交通拠点としての機能が高まります。
グランドデザイン大阪では、新大阪駅と大阪駅周辺を別々の点ではなく一つの大きなエリアと捉え、大都市間をつなぐ大阪都心の玄関口としての機能を生かすとしています。うめきた二期地区の整備でも、淀川にもつながるみどりのネットワークを形成するとのまちづくりの方針が示され、さらに淀川を超えて新大阪方面に伸ばしていくよう取り組まれているとお聞きしております。
さらに、グランドデザイン大阪には、新大阪と大阪を一体化する中長期の取り組みとして、淡路・新大阪・大阪に至る連絡鉄道が挙げられており、新大阪と大阪の一体化を図るのが重要と考えます。
そこで、グランドデザイン大阪が目指す新大阪と大阪の一体化に当たり、この連絡鉄道について今後どのように取り組むのでしょうか、住宅まちづくり部長に伺います。
スライド4
スライド5
新大阪、大阪の一体化についてでございますが、新大阪駅と大阪駅の周辺は、さまざまな都市機能が集積をいたしますストック、そしてポテンシャルの非常に高い地域となっております。
グランドデザイン大阪では、新大阪と大阪を一体的なエリアと捉えまして、大阪が東京との二極の一極を担うための成長発展の核となるよう位置づけております。
このエリアでは、今まさに新しいまちづくりの動きがございます。例えば、大阪駅周辺では、現在進められております阪神百貨店、新阪急ビルの建てかえに伴う歩行者専用デッキが完成をすることにより、駅南側から大阪駅の中を通り抜け、うめきたのグランフロント大阪までつながる南北方向の動線ができることとなります。また、東西方向は、阪急百貨店と中央郵便局跡地に計画される施設をデッキで結ぶ工事が進められておりまして、将来は、東西南北全てをデッキで結び、歩車完全分離による安全で安心な新しい人の流れを生み出すということとなります。
一方、新大阪駅におきましても、これまで新幹線などによりまして地域の南北が分断されておりましたため、南側から北に広がるオフィス街や専門学校等へのアクセスは、大きく迂回をせざるを得なかったものが、新幹線の改札口がある3階コンコースと新大阪阪急ビルの整備が完成し、駅北口が新設されたことによりまして、南北の新しい動線が生まれ、人の移動がスムーズになるなど、大阪駅、新大阪駅の周辺では、民間主導による新たな都市空間の形成が始まっております。
こうした民間の動きを生かし、さらに議員がただいまお示しいただきました新大阪と大阪の一体化を進めますためには、グランドデザイン大阪で示します淡路・新大阪・大阪に至る連絡鉄道が極めて重要でございます。大阪府では、その一部を西梅田十三新大阪連絡線として戦略4路線の一つに位置づけたところでございます。現在は、うめきたのまちづくりの中で、関係各方面と駅位置などの協議を進めておるところでございます。
今後とも、大阪府といたしましては、大阪市とともに、淡路・新大阪・大阪に至る連絡鉄道を初めとする取り組みを進めまして、国内外から多くの人々が訪れ、住み、働き、学び、楽しむエリアとなりますよう新大阪と大阪の一体化を実現します。
さまざま質問させていただきましたが、この大阪のまち、私も、自分が知らんだけで、いろんなすばらしいものがあるというのを毎回毎回いろんなことを教えてもらっております。そのあるものをしっかりとつないで、ないところは新たに点を打って、そしてすばらしい大阪をつくれるように頑張っていきたいと思います。
以上で私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。